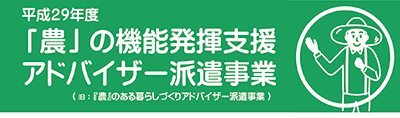第21回園芸福祉シンポジウムinとちぎ
第21回園芸福祉シンポジウムinとちぎ ~公園における園芸福祉~ を開催いたします。
●日 時 2025年6月21日(土)13:30~
●会 場 栃木県宇都宮市 青年会館コンセーレ
栃木県宇都宮市駒生1丁目1番6号
TEL:028-624-1417
https://www.concere.jp/
●プログラム
13:00 受付開始
13:30 開会
【開会挨拶】 吉長成恭(日本園芸福祉普及協会理事長)
茂木正行(園芸福祉とちぎ代表)
13:45 【基調講演】「公園の役割と園芸福祉(仮)」
相田 明 (日本園芸福祉普及協会監事 農学博士(造園)
14:30 休憩
14:45 【パネルディスカッション】「公園の園芸福祉活動事例と今後の展開(仮)」
コーデネーター 吉長成恭(日本園芸福祉普及協会理事長)
パネラー
大出英子(東京農業大学グリーンアカデミー副校長)
茂木正行(園芸福祉とちぎ代表)
設楽 力 (うつくしま園芸福祉の会)
他 調整中
16:45 閉会
17:00~19:00 交流懇親会 会場は閉会時にご案内します
●参加費 シンポジウム 2,000円
交流懇親会 6,000円
●定 員 100名(定員になり次第締切)
●申込締切 5月31日(土)
●主 催 NPO法人日本園芸福祉普及協会
●共 催 園芸福祉とちぎ、うつくしま園芸福祉の会
●お申し込み方法
氏名・住所・TEL・E-mail・所属および交流懇親会の参加不参加を明記の上、kyoukai@engeifukusi.com までお申込みください。
第4回園芸福祉オンラインシンポジウム
第4回園芸福祉オンラインシンポジウムのご案内です。
●日 時 令和7年3月15日(土)13:30~15:30
●開催方法 Zoom
●参加費 無料
●定員 100名 (定員になり次第締切)
●参加資格 初級園芸福祉士および園芸福祉士資格登録者、日本園芸福祉普及協会会員
●申込方法 メールにて、件名「第4回オンラインシンポジウム参加希望」とし
氏名、連絡先(メールアドレスおよび電話番号)を明記の上、kyoukai@engeifukusi.com までお申込みください。
※お申し込みは、初級園芸福祉士および園芸福祉士資格登録者、日本園芸福祉普及協会会員に限らせていただきます。
ご了承ください。
●申込締切 令和7年3月8日(土)
●参加方法 3月10日(月)に参加用 URL をメールにてお送りいたします。
●プログラム
【事例発表】
・デイケア利用者によるリハビリガーデンの活用 遠藤智美さん(東京都)
・JR館山駅東口ロータリー旧駐輪場跡地リノベーション花育福祉プロジェクト 小笠原奈津子さん(千葉県)
ほか1名
【パネルディスカッション】
第19回園芸福祉シンポジウムinくれ 開催報告
令和5年5月27日(土)ビュー・ポートくれ(広島県呉市)にて、第19回園芸福祉シンポジウムが開催されました。
今回のシンポジウムは広島を拠点に活動されているNPO法人緑の風景、ひろしまね園芸福祉協会、植える美ing-ひろしま、みよし園芸福祉ネットワークの皆さんのご協力で、広島はもとより全国各地から約70名の園芸福祉士が集いました。
プログラム立案から当日の開催運営まで中心的にご協力いただいた、ひろしまね園芸福祉協会さんから開催報告が届きました。
第19回園芸福祉シンポジウムinくれ
第19回園芸福祉シンポジウムinくれ
~分かち合おう会える喜び話す幸せ~
日 時 2023年5月27日(土)13:30~16:30
場 所 ビュー・ポートくれ(広島県呉市中通1-1-2)
参加費 シンポジウム 2,000円
交流懇親会 5,000円
定 員 100名
申込締切 5月12日(金)(定員になり次第締め切り)
プログラム
13:00 受付開始
13:30 開会
開会挨拶 小田原裕紀(ひろしまね園芸福祉協会代表)
13:45 基調報告「コロナ禍でも続けた花活とその効果 ~2つのデイサービスでの活動~」
中川勝喜(社会福祉法人的場会常務理事)
進藤丈典(ひろしまね園芸福祉協会理事)
14:30 休憩・種交換会
15:30 グループディスカッション 「Well-being咲かさサミット」
16:00 まとめ・閉会挨拶
吉長成恭(日本園芸福祉普及協会理事長)
16:30 閉会
17:30~19:00 交流懇親会
お申込・お問合せ NPO法人日本園芸福祉普及協会
東京都新宿区市谷薬王寺町58
TEL 03-3266-0666 FAX 03-3266-2667
E-mail kyoukai@engeifukusi.com
主 催 NPO法人日本園芸福祉普及協会
共催(予定) NPO法人緑の風景、ひろしまね園芸福祉協会
植える美ing-ひろしま、みよし園芸福祉ネットワーク
第18回園芸福祉シンポジウムinとうきょう
第18回園芸福祉シンポジウムinとうきょう
~考えよう!スキルと時間の使い方~
開催日 2019年6月15日(土) シンポジウム
16日(日) 見学会 ~皇居東御苑・江戸城跡 ぶらり散歩~
場所 シンポジウム 三茶しゃれなあどホール 世田谷区太子堂2-16-7 三軒茶屋駅より徒歩1分
見学会 皇居東御苑
プログラム
6月15日(土)
10:30~11:30 日本園芸福祉普及協会 通常総会
13:30 シンポジウム受付開始
14:00 開会
基調講演「高齢社会と園芸福祉活動への期待」
坂東眞理子 昭和女子大学 理事長・総長
座談会「充実した人生の後半戦」
進行役 吉長成恭 日本園芸福祉普及協会理事長
17:30 閉会
18:00 交流懇親会
16日(日)
10:00 皇居大手門入口集合
10:30 皇居東御苑見学(ガイドツアー)
12:30 解散
参加費 シンポジウム 2,000円
交流懇親会 5,000円
見学会 無料
定員 150名(定員になり次第締め切り)
締切 5月17日(金) 定員まで余裕がありますので、締め切りを延長しております。
主催 NPO法人日本園芸福祉普及協会
共催 園芸福祉首都圏ネット
お問合せ・お申込み
NPO法人日本園芸福祉普及協会 事務局
東京都新宿区市谷薬王寺町58-204
TEL 03-3266-0666 E-mail kyoukai@engeifukusi.com
第17回園芸福祉シンポジウムinおかやま
第17回園芸福祉シンポジウムinおかやま
~人と人がつながる園芸の輪~
開催日 平成30年6月9日(土) シンポジウム
10日(日) 見学会
場 所 シンポウジム ピュアリティまきび 岡山市北区下石井2-6-41 岡山駅より徒歩7分
見学会 岡山後楽園
プログラム
6月9日(土)
午前 NPO法人日本園芸福祉普及協会 通常総会
13:00 シンポジウム受付開始
13:30 開会 挨拶
13:50 基調講演 「福祉の心は園芸にあり」
社会福祉法人旭川荘 理事長 末光 茂氏
15:05 事例発表 ①「障害児施設における野菜・稲づくりと食育」
旭川荘わかくさ学園 藤井順子
②「グループホーム吉備」での園芸福祉活動~10年の歩み~
グループホーム吉備 橋本紀子ほか
15:45 ミニワークショップ 「スプラウトを作ってみよう!」
柴田幹人
16:50 閉会
17:30 交流懇親会
10日(日)
9:00 岡山後楽園見学 ガイドツアー お田植祭り見学
11:30 解散
参加費 シンポジウム 2,000円
交流懇親会 5,000円
見学会1,000円
共催 NPO法人日本園芸福祉普及協会 NPO法人岡山園芸福祉普及協会
後援(予定) 岡山県 岡山市 社会福祉法人旭川荘 山陽新聞社
第16回園芸福祉シンポジウムinおきなわ
第16回園芸福祉シンポジウムinおきなわ
~ホッと、美ら結い、おーきな輪!~
今回のシンポジウムのテーマ「ホッと、美ら結い、おーきな輪!」とは
ホッと:気温も気持ちの暖かさとホッとする安らぎを表現
美ら結い(ちゅらゆい):沖縄では「結い」は助け合いを表し、麗しい助け合いの意味
おーきな輪:園芸福祉の仲間と手を取り合って大きな活動に広げていくこと
を表現しています。
日 程 平成29年7月8日(土) シンポジウム
9日(日) 見学会
会 場 沖縄県市町村自治会館(2階ホール)
沖縄県那覇市旭町116-37
参加費 シンポジウム 2,000円
交流懇親会 4,000円(予定)
見学会 2,000円
申込方法 沖縄県内在住者:沖縄園芸福祉協会
沖縄県外在住者:日本園芸福祉普及協会
プログラム
7月8日
午前 NPO法人日本園芸福祉普及協会 通常総会
13:30 シンポジウム開会
13:50 講演「沖縄の食文化と植物」(仮題)
15:10 ワークショップ
①アダン筆づくり 植物繊維の筆づくり体験
②草玩具づくり 草を編んで籠やバッタづくり体験
③ハーブを楽しむ 沖縄ハーブと島野菜で美味しい体験
17:00 閉会
17:30 交流懇親会
7月9日
9:00 出発
貸切バスで那覇市内の街路樹や首里城周辺、末吉公園などを廻る、
通常の観光では見られない植物ガイドツアー
12:00 解散
主 催 NPO法人日本園芸福祉普及協会
共 催 沖縄園芸福祉協会
第15回園芸福祉シンポジウムinみえ
第15回園芸福祉シンポジウムinみえのご案内
第15回園芸福祉シンポジウムは、三重県多気町にて開催いたします。今回のシンポジウムを共催する三重県立相可高等学校は、専門教育の高等学校として全国に名を馳せ、園芸福祉分野でも認定校として12年間に350名近くの人材を育成しています。そして、行政や農協、民間製薬会社と連携して『まごころコスメ』シリーズを企画・開発し、そこで得た資金を園芸福祉に使う継続的活動を行っています。また、三重県は、障がい者の農業分野への就労が官民で進められています。
今回のシンポジウムでは、教育とビジネス、障がい者就農をキーワードとし、園芸福祉活動がもたらした社会的インパクト(効果)をテーマに、発表や報告、討議を行います。多くの方の参加をお待ちしております。
日 時 平成28年6月18日(土) 14:00~16:55
場 所 多気町民文化会館
三重県多気郡多気町相可1587-1
参加費 1,000円(高校生は無料)
申込締切 5月18日
主 催 NPO法人日本園芸福祉普及協会
共 催 三重県立相可高校、(一社)三重県障がい者就農促進協議会
問合・申込 NPO法人日本園芸福祉普及協会
TEL03-3266-0666 E-mail kyoukai@engeifukusi.com
第14回園芸福祉シンポジウム
第14回園芸福祉シンポジウム ~園芸福祉 未来への提言~
日 時 平成27年6月13日(土) 13:00~17:00
場 所 住吉公園 体育館 大阪府大阪市住之江区浜口東1-1-13
参加費 1,000円
申込み 参加申込書に必要事項を記入の上、園芸福祉シンポジウム実行委員会事務局宛にFAXまたは郵送にて
お申し込みください。
申込締切 平成27年6月6日(必着)
申込・問合せ先
園芸福祉シンポジウム実行委員会事務局
NPO法人たかつき 担当:石神
〒569-1051 大阪府高槻市原2235
TEL:072-689-9112(受付時間 月~土 9:00~17:30)
FAX:072-658-2204
mail:info@npo-takatsuki.org
プログラム
13:00~13:10 開会式
13:10~14:10 基調講演「自然・社会・経済・文花の持続性は4つの多様性から
-これからの園芸福祉活動は”みんなちがっていい”の発想で」
進士五十八氏 造園家・農学博士・東京農業大学名誉教授
14:20~15:00 様々な分野からの実践発表
15:10~16:10 グループディスカッション
①公園での実践
②病院での実践
③地域活動での実践
④教育機関での実践
⑤農業での実践
※参加者は好きなグループを選んで参加
16:20~16:50 総括(進士五十八氏)
主 催 園芸福祉シンポジウム実行委員会
協 賛 東邦レオ(株)、(株)美交工業
後 援 大阪府、NPO法人日本園芸福祉普及協会、NPO法人園芸療法研究会西日本(予定)
第13回園芸福祉シンポジウムinとうきょう
第13回園芸福祉シンポジウムのご案内
来る6月28日(土)13時30分より東京農業大学横井講堂にて、第13回園芸福祉シンポジウムinとうきょうを開催いたします。Green Nature Human Nature の訳本出版記念を兼ねて、植物と人間の絆を考えます。
日時 2014年6月28日(土) 13:30~16:40
会場 東京農業大学 横井講堂(アカデミアセンターB1)
東京都世田谷区桜丘1-1-1
プログラム
(1) 基調講演 「練馬区大泉の畑から」(仮題)
白石好孝氏(白石農園 大泉風のがっこう代表)
(2) 絆談義 「植物と人間とのさまざまな絆」
進行役:吉長成恭当協会理事長
定員 200名(定員になり次第締め切ります)
参加費 当協会会員 3,000円(資料・新刊本1冊含む)
非会員 5,000円(同上)
申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上、メールまたはFAXで。
申込締切 6月13日(金)
申込先 NPO法人日本園芸福祉普及協会
FAX:03-3266-0667 E-mail:kyoukai@engeifukusi.com
主催 NPO法人日本園芸福祉普及協会
共催 園芸福祉首都圏ネット
※シンポジウム終了後17時より、東京農業大学校内食堂にて交流懇親会を開催します。